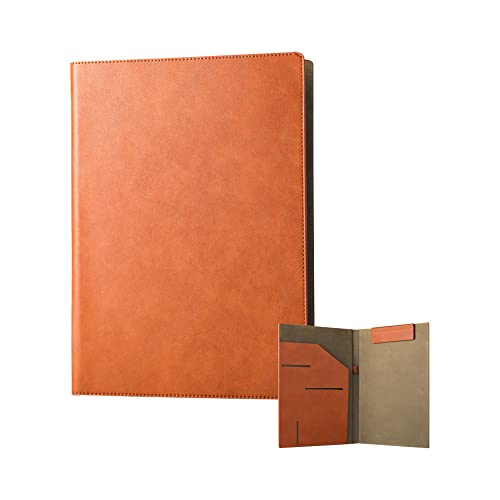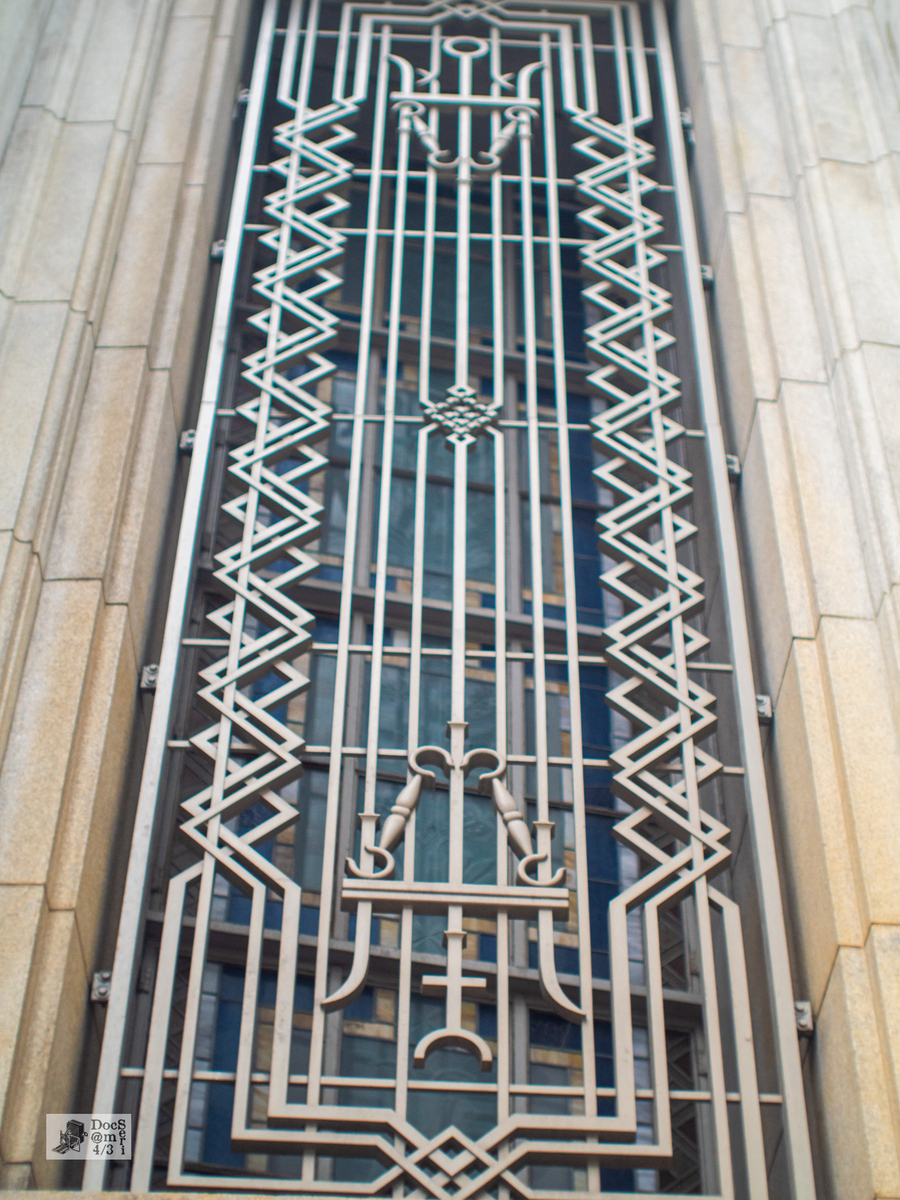先日、Twi⋯⋯𝕏上で、「おぞましい設定のSF」というタグが話題になった。
そういう文脈で出すのもなんだが、おぞましい設定を持った素晴らしいSFのことを思い出したので紹介したい。
作品の舞台設定について明言はないが、登場人物の名前などから日本と推定される。
序盤のニュースなどから、生体工学がかなり発達した未来社会であり、複数の動物を混ぜ合わせた「キメラ」はおろかヒト胚を操作し動物と混ぜ合わせた[愛玩動物]すら作り出されていること、また警察や政府官公庁が企業の言いなりであるらしいことが窺える。
主人公が船で暮らしており、立ち寄り先が水面に突き出したビルの屋上に建てられたバラック群であることから、地球温暖化が進行し海面がかなり上昇しているらしいことがわかる。恐らく居住可能な陸地の減少に伴い地価は高騰、陸地は富裕層のみが暮らす場所となっていること、経済階層が二極化し貧困層はまともに扱われていないだろうことなどが想像できる。いわゆるサイバーパンク(核となる技術領域がではなく

一般にテクノパンクSFでは人体の改変技術が進み、そのことでヒトのアイデンティティが曖昧になった世界が描かれる。またヒトのアイデンティティ境界がおざなりに扱われる理由として、営利主義が行き過ぎて利益のためには法倫理が簡単に踏み躙られるような社会構造が描かれ、ゆえに企業が政府よりも強い力を持っていることが多い。
「螺旋じかけ」世界でもそれは同様だが、特徴的なのは[ヒト以外の生物の特徴を発現した]人間が少なからず存在する点である。なぜそのようなことが生じたのかは最後になって説明されるが、遺伝子工学の行き過ぎが生じた弊害であることは疑いない。
そして階層の二極化や政府の弱体化などによる利益偏重・人権軽視が合わさった結果として、[純粋な人間]を優遇し[ヒト以外の形質が多い]者を排除する優生思想が強まり、非ヒトの形質割合が一定量を超えた者は動物と見做され人権を失う法が成立しており、それを利用してバイオ企業は[あらかじめヒトの形質割合を抑える]ことでヒトの肉体に近い実験体を[製造]したり、金持ちの求めに応じてオーダーメイドの[愛玩用亜人]を作り出している。実に「おぞましい設定」ではないか。


主人公オトはモグリの[生体操作師]である。
非ヒト形質を有する者たちは、発現が進行すれば[処分対象として密告を受ける]ことになる。軽微であっても外観の目立つ者は差別され、陸で暮らしてゆくことは難しく、必然的に水上バラック地域居住者たちは高い割合で非ヒト形質を有する。
多少外見が変わる程度のことならば生存にそう支障はないが、内蔵などに非ヒトの形質が発現すれば健康に影響を及ぼす場合もあるし、また外見のみであっても体表面積の4割以上に非ヒト形質が見られればもはやヒトとは見做されなくなる。
貧民たちの中には警察と通じて密告で小銭を稼いだり、バイオ企業に実験体として売り渡すようなヤクザ者もおり、ゆえに形質の発現を抑制/除去/ごまかしたいという需要がある。
オトはそうした人たちの需要に応え、遺伝子検査をごまかすためにちょっとした生体操作を加えたり、目立つ形質異常箇所を除去するなどして彼らの生存を助けている。
また、オト自身も重度の異種キャリアであり、もはや何が混ざっているのか自身でもわからない、生物との接触や食べ物の成分でさえ形質を暴走させてしまう体質である。彼はその体質を生かして自身を実験体に異種遺伝子の治療方法を開発している。
ヒトとそれ以外の区別が恣意的に線引きされ、ヒトから生まれてもヒトでない者に堕とされる時代。人をヒトとして扱わぬ者たちと、ヒトとして扱われぬ者たちの、どちらが人らしいか。人は生命に、どこまで手を出して良いのか。
おぞましき設定の上にこそ浮かび上がる、真摯で優しいSF。
:書きかけで1ヶ月半ぐらい放置していたのだが、2024年の星雲賞候補作となったそうなのでこの機会にと航海。
































![[スリーピングシープ] キャンバス トートバッグ小ぶり お遍路 バッグ グッズ 機能 内防水 仕切りあり 2way ショルダーベルト付き ポケット (修正版 アイボリー) [スリーピングシープ] キャンバス トートバッグ小ぶり お遍路 バッグ グッズ 機能 内防水 仕切りあり 2way ショルダーベルト付き ポケット (修正版 アイボリー)](https://m.media-amazon.com/images/I/41yqYLmY23L._SL500_.jpg)